わんちゃんとの旅行やドライブ、するほうも外から見るほうも幸せな気持ちになりますよね。
お出かけの時も一緒に居たい。そう思う飼う主さんも多いかと思います。
さて、みなさんはどのくらいの頻度でわんちゃんをドライブに連れていきますか?
「愛犬とのお出かけ・ドライブに関する調査2017」~ホンダアクセス調べ
| どのくらいの頻度で愛犬をドライブ(クルマに乗せてお出かけ)に連れて行く? |
| 1週間に1回:13.2% |
| 1ヶ月に1回:13.7% |
| 2~3ヶ月に1回:12.9% |
約半数の飼い主さんたちが、月に1回以上はドライブに連れていっているという統計がでています。
うちのわんずたちは、だいたい週に一回は大きな公園までドライブがてらお散歩へ行きます。
仕事の日は近所でのお散歩がメインとなってしまいますが、ボーダーコリーの天の『車追い』もあるため、時間のある時は”車の来ない公園”でゆっくりとお散歩をしたい、という安全面の理由もあります。
しかし、ドライブに行く一番の理由は、わんずたちが車でのお出かけが大好きだからです。
ただ、ここで一つ問題がありました。
シェルティーのしおんは、極度の『車酔い』をする子でした。
そんなしおんの車酔いの経験を踏まえて、今回はわんちゃんの『車酔い』についてお話しさせていただきます。
わんちゃんの『車酔い』に悩む皆さまにとって、少しでも参考になれば幸いです。
犬も車酔いする?
車酔いの原因
わんちゃんも人間も、『車酔い』の原理は同じです。
平衡感覚をつかさどる三半規管が、車での揺れや振動などの刺激に対応できずに起こります。
目から入る情報(景色の動きなど)・内耳からの情報(三半規管など)・体からの情報(筋肉や関節)が、
揺れや加速、刺激によって脳に届く情報とズレが生じます。
その結果、脳及び自律神経が混乱し、車酔いを招きます。
車酔いの症状
わんちゃんの車酔いの症状には、下記のようなものがあげられます。
<初期症状>
- しきりにあくびをする
- そわそわして落ち着かなくなる
- 心細げに鳴く
- 吠える
<中・重度症状>
- よだれを垂らす
- パンティング(速くて浅い呼吸)
- 震える
- 嘔吐
- 下痢
- ぐったりする
車酔いそのものによる死の危険性はないと言われていますが、嘔吐による低血糖や脱水症状が起こる危険性が十分考えられます。
中・重度の症状になる前に、こまめに休憩をとるなどをしてわんちゃんの体の負担を軽減させてあげることが大切ですね。
車に酔う犬の割合は?
わんちゃんの車酔いに関して、下記の調査結果があります。
100名の獣医師に伺ったところ、車酔いをする犬は「1割程度」「2-3割」が最も多いという回答が得られました。「4割」以上、また「9割以上」という回答もありました。車に酔う犬は、意外と多くいそうです。
Vet’s Eye[なんとかしてあげたい犬の車酔い。予防や対策は?]より引用
おおよそ、4頭に1頭の割合で、車酔いをするわんちゃんがいるという印象です。
一度でも車酔いをしたことのあるわんちゃんは、それを嫌な経験として記憶してしまいます。
その結果、車に乗る雰囲気やエンジン音、匂いだけで不安な気持ちでいっぱいになってしまい、乗車後わずか数分で酔ってしまう場合もあります。
わが家のわんずにおいても、先代犬を含めると5頭中1頭が車酔いをしますので、平均的な割合といったところでしょうか。
車酔いの対策
車酔い対策で出来ること
車酔いをするわんちゃんや、車嫌いなわんちゃんを、無理に車に慣らせる必要はないと思います。
しかし、動物病院へ行くときや、どうしても移動が必要なケースというのは出てきてしまいます。
その時の為に、少しでもストレスを軽減させてあげたいですよね。
<車酔いを軽減するために出来ること>
- 食事の調整
- 食後すぐの乗車は吐きやすくなるため、1~2時間前に食事を済ませましょう。どうしても直前になる場合は、量を調整し複数回に分けるなどしましょう。
- 車内温度の調整
- 人間が快適と思う温度でも、わんちゃんには暑すぎる場合があります。温度が高いと気分悪くなりやすいので、様子をみながら少し低めの温度設定にしてあげるなどして調整してあげましょう。
- 換気
- 車中は密閉状態になるので、ニオイがこもりやすいです。また、排気ガスのにおいが吐き気を誘発する可能性もあります。こまめに換気をしましょう。
- 芳香剤やタバコ臭などは、嗅覚の優れた犬にとっては刺激が強いため避けましょう。
- こまめな休憩
- 車酔いの症状が悪化する前に、こまめに休憩をとり気分転換をさせてあげましょう。
- 乗車前の運動
- 乗車前に運動させることで、乗車中に疲れて寝てくれれば車酔いを防げる可能性が高いです。
- 声掛け
- 不安な状態にいるわんちゃんに、定期的に声掛けをして安心させてあげましょう
- 声掛けをすることで、すこしですが車酔いから気持ちをそらせてあげられます
- 酔い止め薬
- 酔い止め薬を飲ませて予防する方法もあります。ただし、薬の効果には個体差があり、必ず聞く保証はありません。また、薬ですのでわんちゃんの体に負担を与えることもあります。アレルギーや持病などがある際は市販の酔い止めサプリメントではなく、獣医師さんと相談の上で処方してもらった方が安心かと思います。
- 緩やかな運転
- 急ブレーキや急発進、急ハンドルは車酔いには大敵です。スピードを出さず、緩やかな運転を心がけましょう。
車酔い対策グッズ
<クレート>
動いている車内でわんちゃんをフリーにしておくことは危険ですので、なるべくクレートに入れてあげましょう。
<ラゲッジマット>
もし車中で吐いてしまっても、ラゲッジマットがあれば安心です。
わんちゃんの乗り降りの際も汚れを気にしないで済むので快適な車旅にはお勧めです。
防水・滑り止め機能があり、しっかりと固定できるものが安心です。
<ポータブル扇風機>
わんちゃんのいる後部座席までエアコンを十分にきかせるのって、なかなか時間がかかりますよね。
ポータブル扇風機でエアコンの空気を循環させてあげることで、均一な温度になりやすいです。
風が分散されることで、わんちゃんに直接風が当たることなく快適な温度調整が可能になります。
USB充電が出来、クリップ式のもののほうが角度を自由に変えられるため、使い勝手が良いです。
車メーカーのわんちゃんドライブグッズ
最近では、車メーカーさんでも”わんちゃん用ドライブアクセサリー”を販売するところが増えてきましたよね。
インターペットなどでも展示・紹介されている「HONDA DOGシリーズ」は、わんずたちと過ごす時間や場所の可能性を広げてくれる存在です。
やはり、ドライブグッズは純正のほうが安心感がありますよね。
今後も、いろんなドライブグッズを発売してくれることを期待しています。
多頭飼いの私たちが最終的に選んだ車はHONDA車でした。
HONDA DOGだけが決め手ではなかったのですが、後押しになったのは間違いありません。
2台ともに、ドッグエンブレムを使用しています。
『多頭飼いの車選び』に関しては、下記の記事で詳しく紹介しています。
わんちゃんのことも考えてくれているメーカー、というだけで親近感がわきますよね。
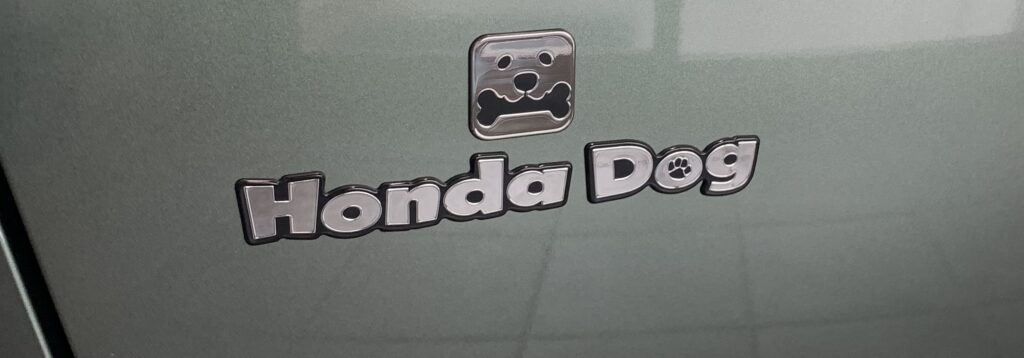
HODA DOG詳細はこちら→https://www.honda.co.jp/ACCESS/dog/
しおんの車酔い改善トレーニング
シェルティーのしおんを迎え入れるまで、わんちゃんにも『車酔い』があることを、わたしは
恥ずかしながら知りませんでした。
先代犬であるボーダーコリーのかのんは、最初から車が大好きで自ら乗り込むほど。
もちろん、『車酔い』の素振りもなく、長距離もなんなく乗りこなしていました。
わんちゃんの『車酔い』の存在を知ったのは、しおんを迎え入れた初日でした。
しおんの引き渡しが済み、家までのわずか10分程度の距離でしおんは豪快に嘔吐をしてしまいました。
最初は、緊張しているからかな?と『車酔い』とは関連付けていませんでしたが、その後車に乗せるたびに『車酔い』の症状が出たため、そこで初めて『車酔い』だと気が付きました。
車酔いの症状
しおんは極度の『車酔い』でした。
乗車後、発車する前にすでに”パンティング(速くて浅い呼吸)”と”よだれをたらす”といった
車酔いの中期症状が出てしまいました。
乗車後3分程度で限界を迎え、5分ともたずに吐いてしまうほどです。
こまめに休憩をはさむといっても、これでは永遠に目的地にはたどり着けません。
そんなさなかで引っ越しが決まり、片道5時間ほどの長旅を、しおんに耐えてもらわなければならなくなりました。
かかりつけの獣医さんに相談し、その日は『酔い止め薬』を飲んで出発しました。
しかし、酔い止めの効果は薄く、一回目の休憩にも間に合わずしてしおんは吐いてしまいました。
引っ越し先はとても田舎の為、どこに行くにも車が必要となります。
車に乗らなけらば、病院にも買い物にも行けません。
そのため、車酔い改善トレーニングを開始することにしました。
トレーニング内容
まずは、しおんの車内での”体制”と”様子”をよく観察しました。
そこでわかったことは、下記の2点でした。
①ずっと立って四つ足で踏ん張ろうとしているため、ふらふらしてしまう
他のわんずは、座ったり伏せたりしているため多少の揺れにも動じませんが、しおんは車への苦手意識から落ち着きがなく、ずっと立ったままでした。そのため、余計に不安定な体制になり酔いやすいことが分かりました。
②外の音を怖がって落ち着かなくなる
基本的に車酔いの予防策として挙げられる、『窓を開けて換気をする』をいう行為は、音に敏感なしおんには逆効果でした。
ただでさえ、車への不安があるうえで窓の外を行きかう車やトラックの走行音はしおんを余計に不安にさせました。
以上の2点を踏まえて、トレーニングを開始しました。
一番大事なことは、『車に乗るといいことがあるよ!楽しいことがあるよ!』ということを覚えてもらうことでした。
しおんは、ボール遊びが大好きでしたので、目的地は広い公園です。
ついたら必ず、大好きなボール遊びをします。
2番目に大事なことは、『帰り道は疲れて寝てもらうこと』でした。
人間も同じですが、寝てしまえば車酔いはしません。
沢山遊んで、楽しい気持ちで寝ている間に家に到着。
この繰り返しで、しおんはだんだんと車に乗っていられる時間が伸びていきました。
だんだん車に乗ることに慣れてきたしおんは、車中でお座りしたり伏せたりも出来るようになってきました。
そのタイミングで、『クレート』『ドライブベッド』での移動の練習をしました。
最初のうちは、わたしたちのほうが心配でそわそわしていました。
抱っこならば、息遣いやよだれの様子などをすぐに把握できますが、後部座席のクレートやベッドではしおんの様子は逐一確認が出来ません。
しかし、休憩の感覚を短くして頻繁に様子をうかがいながら進むことで、だんだんと慣れていきました。
トレーニングの成果
トレーニングを繰り返し、3年ほど経過したころ・・・・。
高速道路だけのまっすぐな道のりであれば、片道3時間は乗っていられるようになりました。(※途中休憩2~3回を含む)
そんなしおんの成長を見て、私たちは旅行を計画しました。
目的地は往復5時間ほどの「わんちゃんと泊まれる宿」です。
半分は高速道路ですが、残り半分は市街地を走ります。
帰り道は寝てくれるだろう、ということで心配はしていませんでしたが、
問題は行きの道のりです。
結果は、しおんは一度も吐くことなく、とても楽しい旅行となりました!!
その旅行を皮切りに、片道3時間以上かかる実家への帰省や少し遠方公園などにも行けるようになりました。
もちろん、完全に克服したわけではなく、山道などのくねくね道はいまだに酔ってしまうので、必要がない限りはそのような道は使わないようにしています。
飼いぬし側で、行く場所や行くまでの道のりはある程度精査できるので、
時間が余分にかかってもまっすぐな道を選んだり、料金はかかっても整備された道を選ぶなどをして、しおんの負担を可能な限り軽くしてあげています。
帰省や旅行なんて無理だと諦めていましたが、しおんがトレーニングを頑張ってくれたおかげで、
みんなでお出かけすることが出来るようになりました。
諦めず、トレーニングを続けてよかったと思うと同時に、頑張ってくれたしおんに感謝しています。
まとめ

現在、しおんは6歳になりました。(2022年時点)
車に乗ってすぐに息が上がり、5分で車酔いをして吐いていたしおんでしたが、
今では行きの車中でも寝るほどに落ち着くことが出来るようになりました。
車酔いの程度や、トレーニングの成果にはもちろん個体差があるため、今回ご紹介した方法が一概には良いとは言い切れません。
しかし、車酔いの原因を観察し見つけてあげること、取り除ける原因は排除してあげること、
無理のない範囲でトレーニングを行うこと、トレーニングで楽しい思いをしてもらうこと、
これらを基本としてわんちゃんの個性に合わせた配慮とトレーニングを続けることで、少しでもお互いにとって良い環境が作れれば幸せかと思います。
すべてはわんちゃんの為に。
大変さは足し算、楽しさは掛け算以上。
皆さまにとって、素敵なわんわんライフになることを願って。







コメント